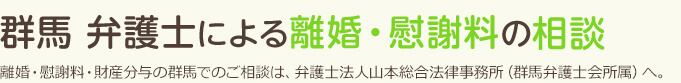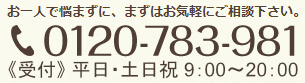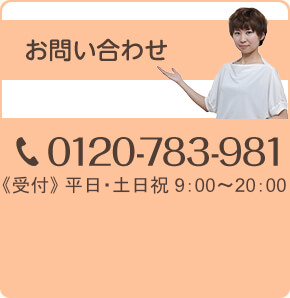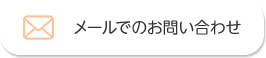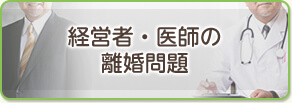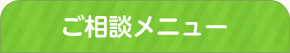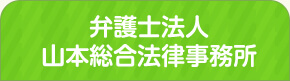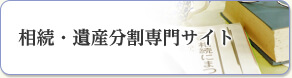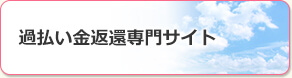経営者・医師の離婚問題

離婚問題は誰にとっても深刻ですが、当事務所の経験では、会社や士業の事務所の経営者、医師の方などの場合、所得が高い故に特有の問題があり、より複雑な事態となることが多い実感があります。
以下では、経営者・医師の離婚相談を多数頂いている弁護士が、高額所得者特有の問題点について、解説していきます。
- 1.財産分与の問題
- 2分の1での分与が原則
- 一方が著しい高収入を得ている場合
- 最終的には夫婦の貢献度を考慮して割合が決定される
- 2.妻が夫の会社や医院を手伝っていることによる問題
- 3.非上場会社の株式価格の評価方法
- 4.非上場株式の財産分与の具体例
- 5.問題がこじれる前に専門家に相談を
1.財産分与の問題
経営者や医師の方が離婚する場合「財産分与」が問題となるケースが多々あります。
2分の1での分与が原則

一般的な事案では、財産分与は夫婦がそれぞれ2分の1ずつ取得します。
妻が専業主婦で実収入がなくても、妻の取得割合を減らされることはありません。
一方が著しい高収入を得ている場合
ただ、夫が医師や経営者の場合には、夫の個人的な資質や能力、努力などにより、著しい高収入を得ているケースでは、財産形成においても夫の貢献度が明らかに高い場合が多いと言えます。
このようなケースにおいてまで、夫婦の財産分与割合を2分の1ずつとすると不合理です。
そこで財産分与の割合が修正され、夫の取得割合が多くされる場合もあります。
しかし、夫の方にどこまでの割合が認められるかという点については、明確なルールがありません。過去には夫が医師の事例で妻の財産分与取得分をわずか5%とした事例などもありますが、必ずそうなるとは限りません。
最終的には夫婦の貢献度を考慮して割合が決定される
結局は、次のような点を考慮して、裁判所が個別に判断することになります。
- 夫にどのような特殊能力があるのか
- それがどの程度財産形成に影響しているのか
- 夫婦がこれまでどのように生活してきたのか
- どのくらい貯蓄をしているのか 等
お一人では適切な対処方法、主張方法がわかりにくいでしょうから、まずは一度、経験豊富な弁護士までご相談ください。
2.妻が夫の会社や医院を手伝っていることによる問題

経営者や医師の方は、妻を会社やクリニックの従業員として雇用しているケースも多く見られます。
その場合、離婚したからといって必ずしも妻を解雇できるわけではないので、注意が必要です。
離婚は解雇理由にならないからです。
離婚後妻に会社や医院を辞めてもらうためには、話し合いが必要です。場合によっては上乗せして退職金を支給する必要などもあるでしょう。
また妻が会社の株式を持っている場合には、離婚の際に買い取っておく必要も出てきます。
3.非上場会社の株式価格の評価方法
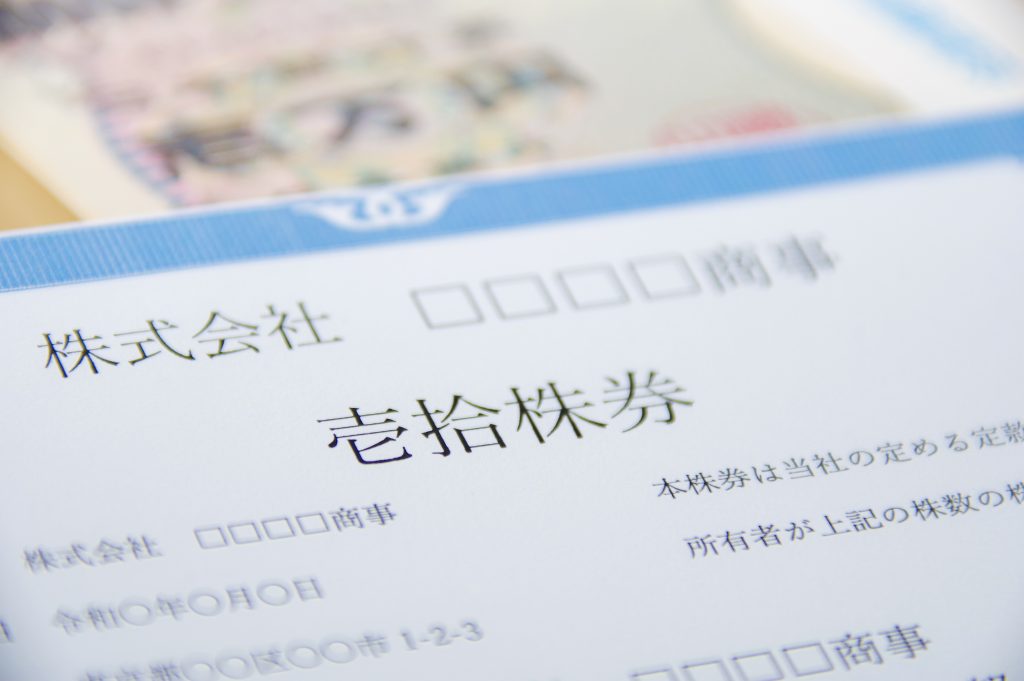
経営者が離婚するときには「株式の財産分与」に注意が必要です。
非上場株式は代償金支払いによって財産分与する
婚姻中に取得した株式は夫婦共有財産として財産分与の対象になるので、夫が経営者の場合には会社株式についても妻に2分の1の請求権が認められます。
しかし非上場株式の場合、妻は株式をもらっても仕方ありませんし、夫の方は離婚する妻に会社の株式を渡したくないでしょう。そこで「代償金」を支払う方法により、解決します。
非上場株式の評価方法
では、その代償金はどのように計算すれば良いのでしょうか?非上場株式の評価方法が問題となります。
非上場株式については、いくつかの評価方法があります。
- 類似業種比準方式
大企業で利用されることが多い評価方法です。類似業種の平均的な株価をもとにしつつ、1株当たりの配当金額や年利、純資産価額を類似業種のものと比較して株式の評価額を算定します。
- 純資産価額方式
純資産額(資産から負債を引いた価額)をもとにして一株あたりの評価額を算定します。中小企業の場合には、類似業種比准方式と純資産価額方式を併用するケースが多くなっています。零細企業の場合には純資産方式のみによって評価するケースが多数です。
- 配当還元方式
株式の配当金額をもとにして株式価格を評価する方法です。同族株主の少ない企業で採用されることが多くなっています。
離婚の際、上記のどの方法を使うべきという決まりはありません。上記の中からその都度適切な方法を選択します。
具体的な計算は非常に複雑ですので、税理士などの専門家に相談して評価してもらいましょう。
4.非上場株式の財産分与の具体例
非上場株式の財産分与について、具体例を挙げて解説します。
夫が中小企業の経営者で妻が従業員の場合(原則的なケース)
夫が中小企業を経営しており発行株式数が5000株、1株あたりの評価額が1万円だったとしましょう。
この場合、株式全体の価額は(5000株×1万円=)5000万円となります。
そこで妻は財産分与として夫に対し、その半額である2500万円を請求できます。
夫の貢献度が特に高いと評価される場合
ただし上記でも説明したように、夫が経営者であり、夫婦の財産形成のほとんどを夫の特段の努力や資質によって実現している場合には、夫の貢献度が特に高かったと評価されます。
すると、原則的な2分の1の財産分与割合が修正される可能性があります。
その場合、妻は2500万円を請求できず、1000万円やそれ以下になることも考えられます。
具体的にいくらになるかは、会社や夫婦の具体的な状況によって異なります。
5.問題がこじれる前に専門家に相談を
以上で述べたように、経営者の方や医師の離婚には、一般の方とは異なる多くの問題がついてまわります。
後に思わぬ不利益を被ることの無いよう、お困りのこと、不明なことがございましたら、お早めに弁護士にご相談ください。
関連リンク
年収が2000万円以上の場合の養育費、婚姻費用の計算方法について