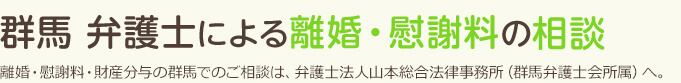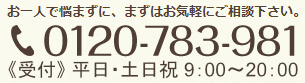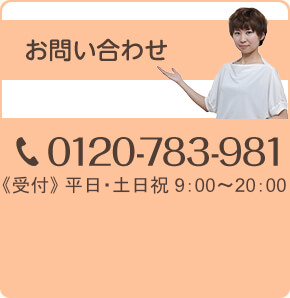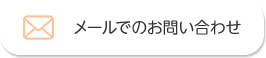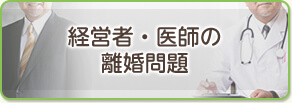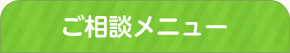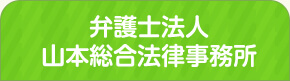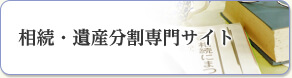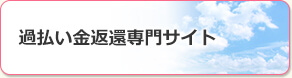離婚後の「面会交流」はどう決める?拒否・制限・申立てまで弁護士が解説

離婚しても、子どもに会う権利はある
「面会交流(面接交渉権)」とは、親権者や監護者にならなかった親が、離れて暮らす子どもと会ったり、連絡を取ったりする権利です。離婚後に限らず、別居中であっても子どもに会うことは原則可能です。
たとえば、離婚の話し合いがまとまらないまま、妻が子どもを連れて実家に戻ってしまった場合でも、夫は家庭裁判所に面会交流の申立てを行うことで、子どもとの交流を求めることができます。
面会交流の基本ルールと手続き
面会交流の決め方
面会交流(面接交渉)の方法や頻度は、まずは父母の話し合い(協議)で決めるのが基本です。
離婚届を提出する際や、離婚後に取り決めが必要になった場合には、以下のような具体的な項目について、できるだけ詳細に決めておくとトラブルを防ぐことができます。
- 面会の頻度(月に何回行うか)
- 面会の時間帯(午前〜午後の何時までか)
- 面会の場所(親の自宅・公園・ファミリーレストランなど)
- 子どもの引き渡し方法(送迎の有無、待ち合わせ場所)
- 宿泊を含むかどうか(宿泊面会が可能か)
- 電話やオンライン通話の可否と頻度(LINE通話やZoomなど)
- 誕生日・クリスマスなど特別な日の対応
- 写真のやりとりやプレゼントに関するルール
口頭での合意だけでは、後に「そんな約束はしていない」とトラブルになることもあるため、可能であれば合意内容を文書にして残すことが大切です。
「面会交流に関する合意書」などの形にしておくと安心です。
【弁護士が解説!】協議離婚と調停離婚どちらを選ぶべき?
話し合いで決まらない場合は家庭裁判所へ
当事者間の話し合いで合意に至らなかった場合や、一方がまったく話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の意見を調整しながら、子どもにとって適切な面会交流の方法を探っていきます。
調停が不成立に終わった場合は、審判手続に移行し、最終的には家庭裁判所の裁判官が、面会交流を実施すべきかどうか、実施する場合はどのような条件が妥当かを判断します。
この際、家庭裁判所は「親の希望」ではなく、あくまで子どもの利益(福祉)を最優先に考えて決定します。たとえば、子どもの年齢、性格、生活リズム、親子関係の状態、別居期間の長さなど、さまざまな事情が総合的に考慮されます。
面会交流の具体例
| 内容例 | 備考 |
|---|---|
| 月1回の対面面会 | 公共の場所や親権者の同伴条件をつけることも可 |
| 夏休みに3日間の宿泊 | 学校の長期休暇に合わせた柔軟な面会が可能 |
| 誕生日にオンライン通話 | 特別な日には対面でなくても連絡の機会を設けることが望ましい |
面会交流を拒否・制限・停止できるのか?
原則は「子どもに会わせる義務がある」
面会交流は、親として当然に認められる権利であり、親権者や監護者が一方的に拒否することは原則できません。
ただし、以下のような事情がある場合には、家庭裁判所が面会交流の制限や停止を認めることがあります。
面会交流が制限される典型的なケース
- 面会によって子どもに精神的な悪影響が出ると判断される場合
- 面会の際に復縁を迫る、金銭を無心する等、不適切な言動がある場合
- 子どもを無断で連れ出す・連れ去るおそれがある場合
- DV歴がある、または子どもや監護親に対して暴力をふるった経歴がある場合
面会交流の条件に納得できない場合の対処法
調停や審判の中で、相手から提示された条件に納得できない場合でも、感情的にならず法的な手続きを通じて見直しを求めることが大切です。
- 家庭裁判所に面会交流の調停申立て
面会内容や頻度を話し合う場を裁判所で設けます。 - 調停で合意できなければ、審判に移行
裁判官が双方の主張をもとに判断を下す手続きです。 - 裁判所が子の福祉の観点から最終判断
子どもの利益を最優先に、面会交流の可否や条件が決まります。
※一度決まった面会交流の内容でも、事情の変化によって「変更」や「一時停止」が認められる場合があります。
弁護士に相談すべきケース
- 相手が一方的に子どもとの面会を拒否している
- 面会交流の条件が過剰で納得できない
- 面会のたびに嫌がらせやトラブルがある
- 子どもに悪影響が出ていると感じている
これらのケースでは、弁護士を通じて調停や審判を申し立てることが適切です。ご自身だけで抱え込まず、専門家にご相談ください。
面会交流に関するよくある質問
A. はい、可能です。たとえ離婚前でも、別居中の親は家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。
A. 面会交流の拒否は原則できません。まずは家庭裁判所に調停を申立て、面会の実施について話し合いましょう。
A. 子どもに精神的・身体的な悪影響があると判断される場合、制限・停止が認められる可能性があります(例:DVや連れ去りの恐れ)。
A. 家庭裁判所の調停や審判で条件の変更を求めることができます。一度合意した条件も事情に応じて見直しが可能です。
A. 子どもの年齢や意思の成熟度にもよります。無理に面会を続けると逆効果となることもあるため、家庭裁判所での判断を仰ぐのが適切です。
まとめ
- 面会交流(面接交渉)は、親である以上当然に認められる重要な権利です。
- 離婚後だけでなく、別居中でも申立ては可能です。
- 面会の方法や頻度は、父母の合意か、家庭裁判所の判断で決まります。
- ただし、子どもに悪影響があると判断される場合は、制限・停止されることもあります。
- 条件に納得できない場合やトラブルがある場合は、早めに弁護士へ相談を。
面会交流をめぐるトラブルは、子どもの健全な成長に影響することもあります。
当事務所では、調停・審判手続の代理から条件交渉まで、弁護士がしっかりサポートいたします。
お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
親権がない親でも子どもと暮らせる?「監護権」でできることとは