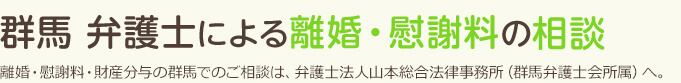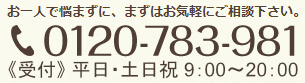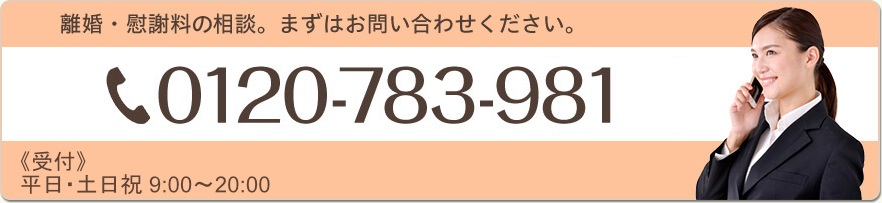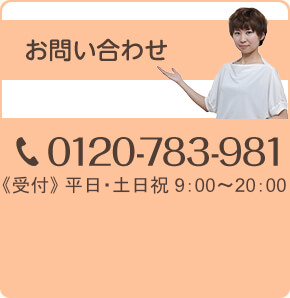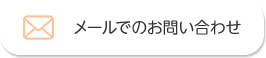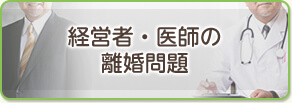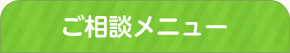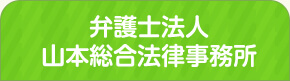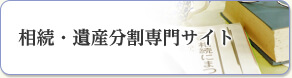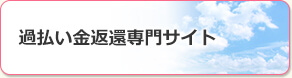離婚時の不動産の財産分与、損をしないためには?知っておくべきポイント
- 執筆者弁護士 山本哲也
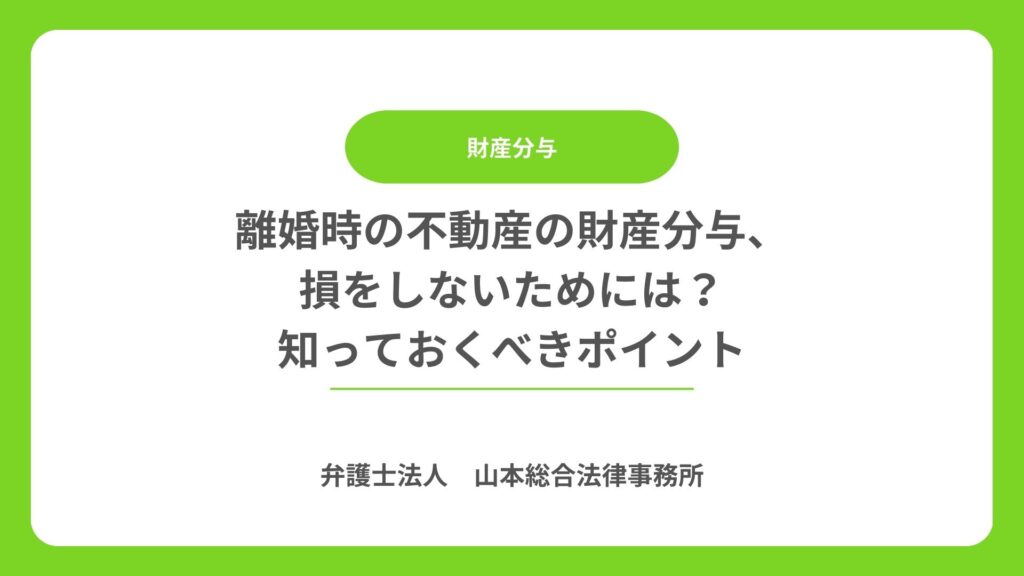
夫婦が離婚する際には、財産分与の請求をすることが可能です。マイホームなどの不動産も、基本的に財産分与の対象となります。
しかし、不動産を物理的に分けることは難しいため、多くの場合は金銭的な解決を図ることになるでしょう。その際、いくつかのポイントに注意しなければ損をするおそれがあることに注意が必要です。
今回は、不動産の財産分与で損をしないために知っておくべきポイントについて、弁護士がわかりやすく解説します。
財産分与とは
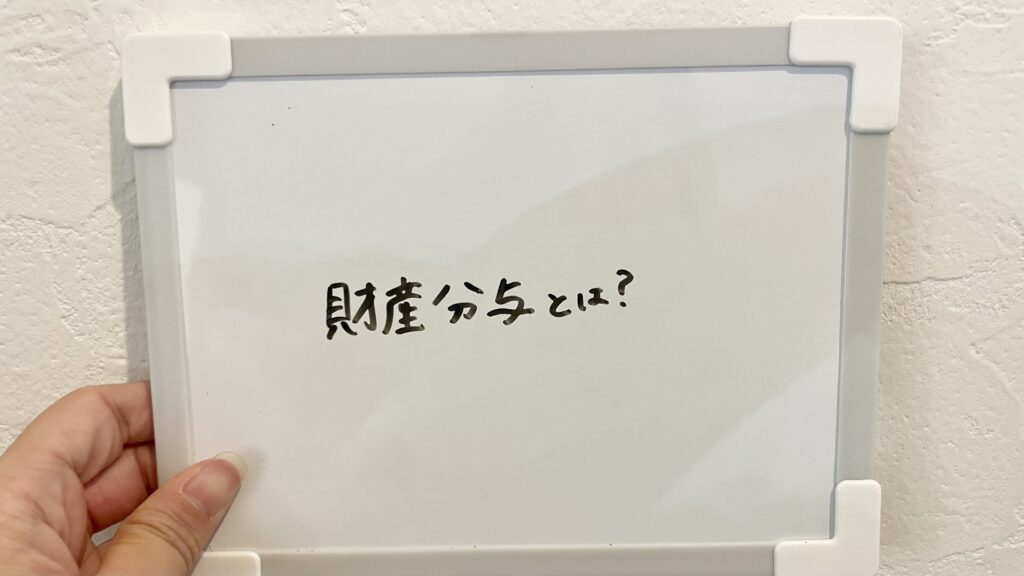
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力し合って築いた財産を、離婚時に分け合うことです。
まずは、財産分与に関する基本的なことを確認しておきましょう。
財産分与の対象となるもの(不動産、預貯金、車など)
婚姻中に夫婦の協力に基づき取得した財産は、基本的にすべて財産分与の対象となります。どちらの名義で購入したのか、どちらが代金を支払ったのかなどは問われません。
一般的に財産分与が行われている財産の代表的なものとして、以下のようなものが挙げられます。
- 不動産(土地や家屋など)
- 預貯金
- 自動車
- 株式(NISA、iDeCoや投資信託も含む)などの有価証券
- 生命保険や学資保険(解約返戻金があるもの)
- 家財道具、家電など
- 貴金属や絵画、骨董品
- 退職金
- 年金
借金などの負債については、夫婦の生活のために生じたものは財産分与の対象となります。しかし、ギャンブルや浪費で作った借金のように、夫婦生活の維持に関係のないものは対象外です。
共有財産と特有財産
婚姻中に夫婦が協力し合って築いた財産のことを、「共有財産」といいます。
これに対して、結婚前から所有していた財産や、婚姻中に取得したものでも夫婦の協力とは関係のない財産のことを「特有財産」といいます。
共有財産は財産分与の対象となりますが、特有財産は対象外です。
特有財産の代表例としては、結婚前に貯めていた預貯金や、結婚後に贈与や相続によって取得した財産などが挙げられます。
不動産の財産分与

ここからは、マイホームなどの不動産の財産分与について詳しく解説していきます。
不動産を財産分与の対象とする場合の注意点
まずは、以下の点を確認しておきましょう。
- 不動産の名義を問わず財産分与の対象となる
- 分与の割合は原則2分の1ずつ
- 住宅ローンが残っていないか
- 連帯債務者や連帯保証人になっていないか
- 財産分与の請求期限は2年
まず、不動産の所有名義が夫婦のどちらか一方となっている場合でも、共有財産に該当する場合は財産分与の対象となります。
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。専業主婦や専業主夫の世帯でも、この原則が適用されます。なぜなら、家事労働にも会社などでの労働と同等の価値があると考えられているからです。
ただし、夫婦の一方が医師や大企業の社長などで、特別な才能や努力で高収入を得ていた場合には、この原則が修正されることもあります。しかし、一般的な会社員の世帯では、ほとんどの場合、財産分与は2分の1ずつと考えて差し支えありません。
住宅ローンが残っている場合には、その残高と、連帯債務者や連帯保証人になっていないかも確認してください。住宅ローンの問題については、後ほど詳しく解説します。
なお、財産分与は離婚後でも請求できますが、離婚が成立した日から2年が経過すると請求できなくなります。できる限り、離婚が成立する前に財産分与の請求をして、夫婦間で合意した内容を記載した離婚協議書を作成しておきましょう。
【参考】離婚とお金の問題
不動産の評価方法
財産分与は共有財産を2分の1ずつに分けるものなので、不動産の価格を正確に評価することが非常に重要です。
しかし、財産分与における不動産の評価方法には、特に決まりはありません。
一般的には、時価(市場価格)を参考にして不動産の評価額を決めることになります。時価を調べるためには、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。各社の査定価格の平均額を、その不動産の評価額とするのが一般的です。
公平に評価額を決めるためには、夫婦それぞれが個別に不動産会社を選び、査定を依頼するとよいでしょう。
固定資産評価額を基準として財産分をする夫婦もいますが、固定資産評価額は時価より低いことが多いため、財産分与を請求する側が不利になりやすいことに注意が必要です。
分割方法
不動産を物理的に分割することは難しいため、財産分与では次の方法のどちらかによって分割することになります。
- 売却して代金を分け合う
- どちらかが住み続け、金銭で精算する
不動産を売却して金銭に換えれば、公平に分割することが容易になります。ただし、適正価格で売却することが重要なので、場合によっては売れるまでに時間がかかるかもしれません。
どちらかが住み続ける場合には、住み続ける側が相手方に対して、評価額の2分の1を支払うことになります。
例えば、夫が時価3,000万円のマイホームに住み続ける場合は、その半額の1,500万円を財産分与として、妻に支払います。
夫婦の話し合い次第では、妻がマイホームを取得する代わりに、預貯金など他の共有財産は分与しないなど、柔軟な形で分割することも可能です。
【参考】【Q&A】離婚したら夫が購入した不動産は誰のものになる?
住宅ローンが残っている場合の財産分与

住宅ローンの残高が不動産の時価より低い「アンダーローン」のケースでは、その差額を2分の1ずつ分けることになります。不動産を売却する場合には、売却代金でまず住宅ローンを完済し、その残りを2分の1ずつに分けることになるでしょう。
住宅ローンの残高が不動産の時価より高い「オーバーローン」のケースでも、基本的には債務が超過している部分が財産分与の対象となります。しかし、借入先の金融機関の承諾がなければ債務者を変更できないため、離婚後もローンの名義人が返済義務を負い続けることに注意が必要です。
このような問題があるため、オーバーローンのケースでは、離婚後の夫婦それぞれの生活設計なども考慮しつつ、柔軟な分割方法を検討することが重要となります。
よくあるケースとして、夫名義の住宅ローンが残っている場合に、夫がその家に住み続けて自分でローンを支払い続けることする方法が挙げられます。
一方では、夫名義の住宅ローンが残っていても妻子がマイホームに住み続け、夫が養育費代わりに住宅ローンを支払い続けるという方法もあります。ただし、この方法によると、夫が住宅ローンの滞納を続けるとマイホームが競売されてしまい、妻子が住む場所を失いかねないというリスクがあることに注意が必要です。
不動産の財産分与に関する税金
財産分与は、基本的に非課税です。
ただし、不動産のように価格が変動する財産を分与する場合には、分与する時点での時価が取得したときの価格より高ければ、その差額に譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税を計算する際には、不動産の時価から、取得した際に支払った代金だけでなく、取得時や譲渡時の手数料などの必要経費も差し引くことができます。
なお、マイホームのような居住用不動産を財産分与する際には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されますので、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことが可能です。
財産分与で譲渡所得税が課せられるケースは少ないですが、思わぬ支出によるトラブルを回避するためにも、事前に譲渡所得の有無を確認した方がよいでしょう。
財産分与を弁護士に相談するメリット

財産分与では、専門的な知識が不足することが原因で損をしてしまうケースが少なくありません。適切に財産を受け取るためには、弁護士へのご相談がおすすめです。
弁護士は、相手方に隠し財産がないかについても調査した上で、財産分与の対象となる財産を洗い出してくれます。各財産の評価についてもサポートしてもらえます。必要に応じて、相手方が財産を使い込まないようにするための法的措置をとってもらうことも可能です。
相手方との交渉は、弁護士に任せることができます。相手方が財産分与に応じようとしない場合や、分与の割合・金額などで意見が対立する場合も、弁護士が冷静かつ論理的に相手方の説得を図ってくれます。
どうしても交渉がまとまらない場合には、速やかに家庭裁判所へ調停や審判を申し立てることにより、法的な解決を図ってもらうことも可能です。
財産分与だけでなく、慰謝料や親権、養育費など、他の離婚条件についても適切なアドバイスが受けられますし、相手方との交渉や法的手続きを任せられます。
弁護士のサポートを受けることで、納得のいく条件で離婚することが可能となるでしょう。
群馬の弁護士法人山本総合法律事務所では、皆様の笑顔を取り戻していただけますように、離婚問題の解決に力を入れております。不動産が絡む複雑な財産分与の解決実績も豊富にございますので、財産分与でお困りの際はぜひ、当事務所までお気軽にお問合せください。
解決事例
未払い生活費を回収し、さらに自宅の土地と建物を取得し離婚できたケース
性格の不一致から離婚を決意した専業主婦の方が、
未払いの生活費をきっちり回収し、さらに住宅ローン付きの自宅(土地・建物)を自分名義にして離婚を成立させたケースです。
弁護士が金融機関との交渉も担当し、親権獲得・養育費の支払いも実現。
ご依頼者様の希望をすべて叶えた解決事例をご紹介します。
【参考】未払い生活費を回収し、さらに自宅の土地と建物を取得し離婚できたケース
- モラハラを受けやすい人の特徴や、やめさせる方法について弁護士が解説
- モラハラで悩んでいる方は山本総合法律事務所の弁護士にご相談を
- モラハラ離婚で慰謝料請求はできる?相場や事例を弁護士が解説
- 離婚した夫が養育費を支払ってくれない場合の対処法とは?回収方法や時効について解説
- 離婚時の預貯金の財産分与はどうなる? 分割割合・注意点・名義を解説
- 株式は財産分与の対象になる?評価方法や注意点などを解説
- 離婚後の子供の相続問題|前妻の子と後妻の間で起こる遺産分割トラブルと対策
- スマホ依存は離婚原因になる?最近増えているスマホ離婚に関して弁護士が解説
- 食い尽くし系の夫と離婚することはできる?
- 【弁護士が解説】2024年5月に民法改正により離婚後の共同親権が認められました